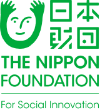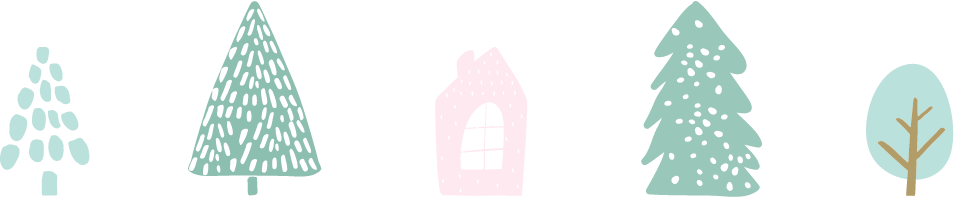「頼る力」とは、一方通行ではなく互いに作用し合うこと

「スペシャルニーズのある子どもと家族支援を考えるシンポジウム」より、主要コンテンツを全4回にわたってお届けするレポート、第3回は「頼る力の育み方」と題したトークセッション。引き続き髙橋氏が登壇し、在宅ケアや産後ケア、産婦人科を舞台にしたドラマ企画者といった多岐にわたる分野からシンポジストを迎え、繰り広げられたセッションの模様をお届けする。
シンポジスト
秋山正子(マギーズ東京、暮らしの保健室)
鈴木早苗(コウノドリ 企画プロデューサー)
吉岡マコ(認定NPO法人 マドレボニータ)
髙橋 昭彦(認定NPO法人 うりずん)
ファリシテーター 日本財団 高島友和
場づくりをする人たちがそれぞれの視点で見る「頼る力」
2つ目のセッションは、「頼る力の育み方」というテーマを掲げた。シンポジストに投げかけた最初のお題は、「頼る力と私」。シンポジストは、自己紹介と共に一人ひとり自分なりの「頼る力」について、話をはじめた。
最初に紹介されたのは、「暮らしの保健室」や「マギーズ東京」の代表である秋山正子さん。前者は、認知症や介護、がん患者の治療や緩和ケアについてなど、地域の方々の身の回りの暮らしや医療、介護といった内容に関して、身近に相談ができる場所であり、後者は、がん患者やその家族が訪れ、その場にいるスタッフや利用者同士と話し、時には一人で過ごしながら、自分を取り戻す場所。気軽に立ち寄れるあたたかさがある場所である。

秋山「私はもともと訪問看護をやっており、その延長線上に、地域で敷居が低く間口は広い相談場所や居場所づくりができないか、と思っていました。それが、『暮らしの保健室』になるのですが、そのベースにあるのは、イギリスの『マギーズセンター』なのです。『マギーズセンター』を知った時、〝自分を取り戻す〟ということを大切にしているところに共感しました。教えるとか、答えを出すのではなく、その人が持っているものを引き出すという考え方。『暮らしの保健室』は新宿区の団地の中にありますが、お菓子屋さんに最近あの人がこないとか、花をよく買いに来る人が今日の調子はどうとかいう話が自然と出てきて、身近な話題から会話が生まれ、お互いが気にかけ支えあうきっかけになっています。何かあれば、そこに行けばなんとかなりそうとか、あの人に頼もうとか、そう思える環境があると、頼る力は自然と湧いて、そして和んでいくのだと思います」
吉岡マコさんは、自らの出産を機に、産前・産後の心身に特化したヘルスケアプログラム「産後ケア教室」をスタートさせ、現在は全国70箇所でこの教室を展開している。また、ひとり親、多胎児の母、障害児の母など、社会的に孤立しやすい母親たちの支援にも着手している。

吉岡「頼る力って、単独では存在しないと考えています。頼る力は、言い換えれば助けてもらう力。これは助ける力とお互いに作用し合います。誰かを助けた経験がある人は、助けることは実は嬉しいことだとわかっています。だから、助けてもらうときも、罪悪感なくその好意を受け取ることができる。そうしたら、また誰か助けが必要な時に力になろうと思う。そうやって循環が生まれるんです。助けられることは、他人と繋がることであり、助けることは自分の力を発揮し、尊厳を持つということではないかと思います。産後は、身体がダメージを受け尊厳を失われる時期です。私の産後ケア教室は、体操をしに来るわけではなく、尊厳と繋がりを取り戻すため、そして、人や自分を助ける力を養うためにいらしていただいています」
鈴木早苗さんは、TBSテレビ制作局ドラマ制作部長であり、産婦人科を舞台にした人気ドラマ「コウノドリ」のプロデューサー。「コウノドリ」制作の裏には、7、8人の監修の先生方とそれぞれ細かいやり取りをしていたのだとか。

鈴木「コウノドリの主人公、鴻鳥サクラ(綾野剛)は、りんくう総合医療センターの荻田和秀先生をモデルにしています。荻田先生が出産後退院した母親と子どもの大変な生活を目の当たりにし、『自分はハブになりたい』とおっしゃっていたのが印象に残っています。出産後に、頼れる先がわからずにどんどん閉じていってしまって、子どもと二人だけの世界で孤立してしまう人っているんです。そういう時に、保健師さんは頼れる存在になるはずだからと、保健師さんの指導も熱心にされていました。その荻田先生の想いから、2017年の最終回は、医師の鴻鳥サクラ(綾野剛)が、『僕はみんなをツナゲル、そういう存在になりたい』と宣言し、助産師の小松留美子(吉田羊)は、出産後の地域、親子とツナガル助産師となるため病院から独立。産科医の四宮春樹(星野源)は、出身地と東京をツナゲル形で病院を離れ地元へ。それぞれツナグ一歩を踏み始める形で最終回を迎えました。」
基調講演でもお話をいただいた「うりずん」の髙橋昭彦さんも、再び登壇くださった。

髙橋「訪問診療で御宅におじゃましたり、個別ケアでいろいろなご家族にお会いすると、お母さんの力は非常に大きいと実感します。その力が出産時には、パワーを使い果たして体力も落ちてしまうし、子どもに障がいがあったりすると本当に大変です。それでも周りからは、あなた親でしょ、なんて言われてしまうことがあります。私たちが場所を提供することで、お母さんたちが集まり、次第につながり、お互いが支え合う場所となります。そこには、うりずんとはまた違う〝社会〟ができており、パワーがあります。」
作用し合うことで、お互いにエンパワメントされていく
「頼る力と私」というテーマで一人ひとりが話した後、さらに、話は人と人とが関わり合い、作用していくことへと展開していく。

秋山「がんになると、一定の時間の中で答えを出さなくてはならない時があります。限られた時間の中で、がんと共に生きる自分に気付き、見出し、前に進めていく。一方的に考えを押し付けることでは成しえません。私たちがやりたいのは、とことんお話を聞いた上で、その人が整理する様を一緒に見守って寄り添うこと。私たちがやっているのは、一緒に考えて、伴走するスタイルです。そうすることによって、私たちもエンパワメントされる感覚があります。支える、支えられるということは循環しているんです」
作用し合うという点でいうと、「コウノドリ」の公式サイト内にある「談話室」というコンテンツも同様だと鈴木さんは言う。
鈴木「『談話室』は、視聴者が投稿するコンテンツです。これまでのドラマの公式サイトでは、俳優さんがかっこいいとか、そういう書き込みしかないのが通常なのですが、コウノドリの場合は特殊で、どこにも言うことができなかったであろう自分の気持ちを吐露する場所になっています。匿名なので書きやすいのでしょうね。帝王切開を普通のお産じゃないと言われて悩んでいた、と書き込んだ人に対して、命がけでお産に臨むんですから帝王切開も立派なお産です、とコメントが書き込まれていたり。死産や流産の方の書き込みに対しては、たくさんコメントされ、そのコメントに更に返事をしたりしていて。それだけでお互いがエンパワメントできているのではないか、と思います。ドラマの制作人や出演者もこれを見ているのですが、そこには介入せずにただただ眺めて、見守っている感じなんです」

言葉に出す、ということだけで、救われることがあると吉岡さんも言います。
吉岡「言語化するということは、自分の尊厳を取り戻すのに一番大事なことだと思いますね。自分の中に留まっていたものを言語化して外に出すことで、他者と繋がることができます。だから、『談話室』のように、言語化できるプラットフォームがあることは、とてもいいと思います」
みなさんの中から出たキーワードは、関わりあうという点で、髙橋さんの基調講演で最後に掲げられた「聴く・出向く・つなぐ」ともリンクしてくる。
「頼る力」は、周りの人と共に育まれる
トークセッションの最後は、この頼る、支援するということについて、それぞれが今思っているキーワードを挙げた。
吉岡「循環ですね。助けられた経験が助けるという経験に繋がったり、助けられるときに、自分の無力さを知り謙虚さを学んだりもします。産後ケア教室では、双子、三つ子のお母さん、障害児のお母さんにも、必要な方には介助ボランティアをつけて参加してもらっています。受講料の全額補助をすることもあります。そこまでするのは、それを外に出るきかっけとして使って欲しいっていう気持ちもありますね。自分が助けられた経験を人に還元する。そういう循環が生まれたらいいなと思います」

髙橋「支援することって、支援する側がマイナスになるのではなくて、受ける側も支援する側もプラス1、プラス1で1+1=2になるといいなと思いながら、今日のお話を聞かせていただていました」
鈴木「『コウノドリ』は、出産した人が誰でも自分のことのように思えるところがあったと思います。18トリソミーの赤ちゃんをドラマの中に実際出したことがあって、それは各方面からいろいろ意見もいただいたのですが、まずはドラマという娯楽の中で知って欲しかったという気持ちがあります。知ることが大事だと思ったんですね。意識的なバリアフリーというか、みんな、自分のことだと思ってほしいし、すごいことではなくて、自分もできるかもしれないよ、と思っていただけたらいいのかなと思います」
秋山「私は、〝隣のおばさん〟でいることかな。隣のおばさんという立ち位置でいることによって、お菓子を持って気軽に来てくれるひともいるし、繋がりが生まれやすいんですよね。〝隣のおばさん〟でい続けたいと思いましたね。」

セッションを通して「頼る力」を紐解いてみたが、単に助けてと声をあげることではない。「身近な繋がり」の中で生まれる自然なコミュニケーションから始まり、その積み重ねがお互いを「気づかうつながり」へと変化し、そのつながりが「頼り頼られる関係」を育んでいく。それは、地域でもいいし、家族でもいいし、好きなことを軸に繋がった仲間でもいい。
その循環により、一人で立っていなければ、という緊張感が解けていくだろう。繋がり合いや、作用し合うきっかけづくりの実践者のセッションとなった。
最終回は、日本財団の「難病の子どもと家族を支えるプログラム」の3年の歩みをお届けします。