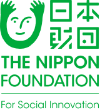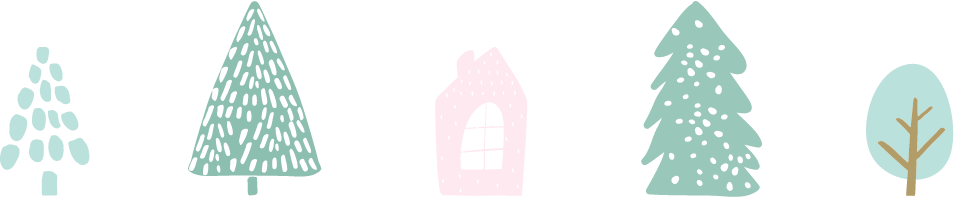子どもの可能性も、自分の可能性も〝決めつけない〟

「スペシャルニーズのある子どもと家族支援を考えるシンポジウム」について、全4回にわたってお届けするレポート。第2回は「30代の現場から見た難病児支援」と題し、様々な角度で難病児支援に関わっているシンポジストを迎えて繰り広げられたトークセッションの模様をお届けする。
シンポジスト
秋山政明(一般社団法人 Burano)
加藤さくら(認定NPO法人 Ubdobe)
松田瞳(社会福祉法人 くるみ)
近藤綾子(こども・子育てケアステーションマム)
当新卓也(厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部)
ファリシテーター 日本財団 中嶋弓子
それぞれの現場で難病児支援に取り組む30代のシンポジストたち
今回のシンポジストは全員が団体の代表者ではない、それぞれ違った現場を持つ30代。難病児の子育てに奮闘する方々の中には、同世代の30代も増えているのだから、私達世代の結婚観や夫婦観、新しい働き方の価値観を持ちながら議論がしてみたい。そんな想いからこの企画が実現した。
それぞれの持つ〝現場〟とは、一体どういったものなのか。
まずは、秋山政明氏。「一般社団法人Burano」を立ち上げ、昨年4月から医療的ケアが必要な子どもや重い障害がある子どもたちのための児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業と、そのお母さん達や地域の一般の女性がともに働くことができるコワーキング事業をはじめた。茨城県古河市の市議会議員としても活躍している。

「2人目の子どもが先天性ミオパチーという筋肉の病気で、生まれた時から呼吸していない状態でした。いざ退院すると、妻は子どもに24時間付きっきりで、介護をしないといけない。職場に復帰できるはずもなく、社会との繋がりがなくなっていきました。子どもに障害があることで、母親の選択肢がなくなっていく状況に疑問を覚えて。それで、子どもを預けて母親が働ける複合施設を作ることを考え、いろいろ視察をして、日本財団ともご縁をいただきました」
加藤さくら氏は、お子さんが福山型先天性筋ジストロフィーであることをきっかけに、「こころのバリアフリークリエイター」として講演・執筆・メディア出演などの活動をスタート。「認定NPO法人 Ubdobe」で、デジタルアートを使ったリハビリプロジェクト「デジリハ」を担当している。

「娘の病気がわかったとき、最初の医療従事者からの言葉が『免疫が弱いのであまり外に出ないように』でした。一方で、主治医からは『病名に振り回されないでください。お子さんが、何によろこび、何をしたがっているのかをよく見て生活してください』と素敵な言葉をかけていただきました。この子にはこの子の人生があるし、私にも私の人生がある。それならお互い楽しく生きたい!と目が覚めたのです。世の中を見渡すと、病名で決めつけられて、生活が制限されることの多さに気づきますね」
近藤綾子氏は、助産師として活躍。2016年に独立し「こども訪問看護ステーションマム」を設立した。NICU退院後の成長発達のフォローや育児支援、早産児や疾患のある子どもの母乳育児支援、哺乳の支援等を担当している。

「助産師は、基本的には正常のお産、正常児を扱うので、なぜここにいるのが疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。私は、総合病院に勤務していたのですが、ある日、退院して2週間で虐待を受けてICUに緊急入院をされたお子さんがいらっしゃいました。その時に、退院のさせ方に疑問を持ち、退院後の支援をしたいと思うようになったのです。現在は、母子・小児専門として、当時一緒に病院勤務していた看護師らと訪問看護ステーションをはじめました」
松田瞳氏は、これまで理学療法士として、病院の重症心身障害児病棟・外来を兼務しながら、未熟児発達相談検診、重い障害がある子どもたちの呼吸・ポジショニングの講義などの活動も行なってきた。現在は、富山県高岡市の「社会福祉法人くるみ」に常勤で勤務している。

「勤めていた病院で身体の変形が重い方がいらっしゃいました。その方は、生まれた時は変形はなかったのですが、寝返りが難しかったことでこうなったのだと。変形が強くなると、様々なリスクが伴います。そのリスクを減らすためにも、小さい時から関わることができたら、と思うようになりました。大きな組織の中だとできないことも多かったので、新しい拠点ができると知って、思い切って転職しました」
当新卓也氏は、厚生労働省で小児慢性特定疾病児童の自立支援事業の創設や、医療費支援の対象疾病の拡大など、患者団体との協議を重ね制度化。現在は、障害児・発達障害者支援室に着任し、発達障害のある子どもの家族支援などを行なっている。
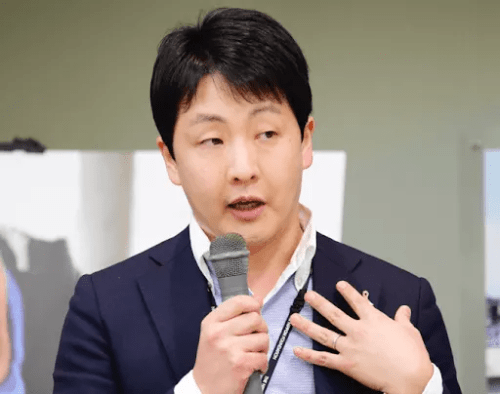
「子どもと関わる事業の配属となり、これまで法改正や自立支援事業をつくることに関わらせていただきましたが、そこで子どもの支援だけではなく、家族の支援も必要だと強く感じました。ポリシーとしては、前例がないからできない、ではなく、家族や普段の視点を入れて事業に携わっています」
ケアや支援というよりは、「チャレンジ」を考えたい
全国を駆け巡りながら、これまで現場の中で聞くケアや支援という言葉に違和感を抱いてきた。マイナスをゼロにするイメージなのだ。子どもの実現したい目標のために、家族も支援者も一丸となってポジティブに取り組めること。それは「チャレンジ」というのではないだろうか。私達が目指していくべき一歩先のチャレンジとは何か。
まずは子ども達のリハビリ活動におけるチャレンジについて、松田氏に聞いてみた。

「くるみには、寝たきりの男の子がいます。その子とリハビリをしながらいろいろなお話をしていく中で、たまたま近くにあるイオンの話題になった時、彼の目が輝いたのです。彼はイオンに行ったことがなかったので、じゃあ一緒に行こうか!と。そして、イオンに行くことを目標にして、そのために練習をし、体調を整えようと話をしたんです。実際に、イオンに行ったら、彼はものすごくドキドキして、心拍が180くらいになっちゃったんですけどね(笑)よっぽど刺激的だったのでしょう。でも、ただ、立つため座るためではなくて、目的をはっきりさせると、本人も挑戦しやすいですよね」
大人が決めたことをやるのではなく、本人に選択させる、本人の意思を尊重して提案できるスタッフでありたい、と松田氏は言う。リハビリの動機づけを高める方法として、デジタルアートをリハビリに取り入れているのが加藤氏。
「大人は骨を丈夫にするためにとか、硬直を和らげるために立たせたいと思ってしまいますが、立位を取りましょうとか、移動のために寝返りを頑張りましょうとか、それだけだと訓練はつまらないし、訓練ばかりという環境は作りたくないんです。できるだけ、本人がやりたいと思って、心が動いたことに対して身体が動く体験をさせたいと思っています。デジタルアートを使ったリハビリ『デジリハ』というプロジェクトをしていますが、例えば、床にデジタルアートの電車を投影すると、そこに座りたくて車椅子から降りるとか、その電車を追いかけたくて寝返りをするとか、そういうことが起こります。エンターテインメント性が加わることによって、子どもにとっても、親にとっても、リハビリが楽しいものになります」

リハビリ=訓練と思うと、親も子どもも疲れてしまう時がある。しかし、発想を変えてリハビリ=楽しい目的を達成するための準備運動だと捉えられると、一気にわくわくして頑張れてしまうから不思議だ。
そして、話題はオンライン上で活用しているツールの話に。
学生時代、物騒な世の中だからと携帯電話を親に持たされ、携帯電話やパソコンは当たり前の環境で育ったデジタルネイティブの私達。共働きも当たり前世代ということで、結婚してすぐにすることは良い家電を買うこと、Amazonの定期便やUberEats、宅配クリーニングのサービスを登録することといった具合だ。
秋山氏は、子どもと一緒に走り回ることはできなくても、iPadを使って一緒に遊ぶことが今の時代ならできると話す。
「うちの子どもは、もうすぐ3歳になりますが、iPadを触って動画をみたり音楽を聴いたりしています。iPadがあることによって、一緒に遊ぶこともできます。VRやドローンも当たり前になってきているので、リハビリはもちろん、さまざまな可能性が広がりますよね」

厚生省でも、スマホ世代を意識した子育て事業を準備していると当新氏は言う。
「厚生省らしからぬ取り組みかもしれませんが、スマホを使って子どもの情報を共有する事業を準備しています。今までは、紙で行なっていたことが、スマホの時代ですから、デジタル技術を使ってできることがあるのではないかと、現在システムを作っているところです」
孤立しがちな医療的ケアが必要な子どもや重い障害がある子どもたちとその家族にとっては、デジタル技術やソーシャルネットワークも、社会と繋がる大きなきっかけになるのだ。
「決めつけない」ことで解放されることがある
最後に、話しのテーマはそれぞれの働き方や生き方にも広がった。
近藤氏は、訪問看護に行く時、自分の肩書きでやることを線引きせずに、お母さんの困っていることに柔軟に手を差し伸べている。
「私は、サポート経験のあるおばさんとして訪問して、離乳食を一緒に作ったり、洗濯物を畳んだりしています。人を家に上げるわけですから、そこにメリットがあると思ってほしいなと。退院早期に人に助けてもらった経験がないと、人を頼らなくなって孤立してしまうと思うんです。それは、看護の領域を超えていると言われたら謝ります。でもそう言われても、私は家庭に入り続け、手伝い続けます」

加藤氏は、子どものことで自分の生き方を決めつけるのではなく、良い意味で〝ジコチュウ(自己中心的)〟に生きていると言い切る。
「自分の子どもが障害児だとわかった時、私の生涯はこの子に捧げなければ、と思いました。でも、やりたいことはたくさんあると気付いた時、ちゃんと自分で主張して発信したら、協力してくれる人がいるかもしれないと思ったんです。それで、5年前に、仕事でもなんでもなく、フランスに行きたいと家族に申し出てみました。すると、家族全員が行っておいでと言ってくれました。両親と夫が子どもを見てくれて、フランス旅行に行くことができたのです。意外に手助けが必要になった時に、助けてくれる人はいるし、サービスだってある。そう気付いたら、自分のやりたいことも言っていいのだと思えるようになりました」
秋山氏も、加藤氏のような考え方は普通で、母親のあり方はもっと多様であってほしいと言う。
「母親はこうあるべき、という価値観を押し付けるのではなく、こうありたいというそれぞれの価値観を大切にすること、そして選択できることが大切だと思います。だからといって、加藤さんのように世の中のお母さん達は子どものことをどうでもいいと思っているわけではありません。日々子どものために頑張り続けていて、その上で自分らしさを大切にできる環境を作りたいですよね」

子どものことも、自分のことも、決めつけない。
どんな子どもの可能性も決めつけずに、その子と一緒に何にチャレンジするのかを考える。そして、そのときに自分が医師や看護師、行政職員、教員、学生だといったことは考えず、立場を超えて「ただの自分」として目の前の子どものために何ができるのかを考えてみる。
そんな循環と連鎖が起こるきっかけに、少しでも今日の自分達がなれたら嬉しく思う。
次回は、セッション2「頼る力の育み方」をお届けします。