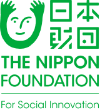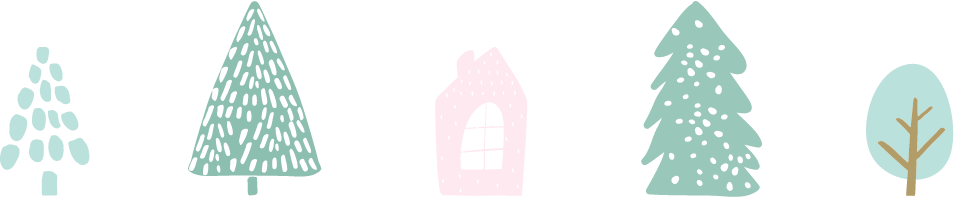どんなに重い障害があっても地域で生きる
NPO法人ソルウェイズ(北海道札幌市)は、「どんな重い障害があっても、地域で生きることができる社会づくり」を目指して、地域に密着した支援を行っている団体です。活動開始は2017年で、札幌市と石狩市に5カ所の重症児デイサービスを開設し、地域の当事者家族のニーズに応える形で生活介護、居宅介護、訪問看護などの事業を拡充しサービスを提供してきました。
代表理事の運上(うんじょう)佳江さんは、4人の子どものうち16歳の長女と11歳の次女が遺伝子の難病を患い、医療的ケアを受けながら生活をしています。
「最初はソルキッズという名称で、子どもたちが通えるデイサービスを親たちと共に立ち上げました。しかし、遠くから通う家族も多く、送迎の負担が大きく非効率的でした。通いたいのに遠くて通えない子どももいる。本来なら、その子の生まれ育った地域で通える場所があった方がいい、ということで、事業所も増え5カ所になりました。お家の方に直接お伺いして子どもたちを診る訪問看護や居宅介護サービスも増やしてきました」と佳江さん。
共同代表で夫の運上昌洋さんは「私たちはデイサービスを提供することが目的ではなく、医療的ケアが必要な子ども家族の生活のなかで『当たり前のことが当たり前にできる』ということを目指しています。訪問支援の事業にも取り組みましたが、家族が休息をとるためには夜間の預かりができるショートステイが必要だと痛感、2022年から『北海道で暮らす医療的ケア児の未来を拓くプロジェクト』として動き始めました。」

計画は着々と進めましたが、ショートステイ設立のハードルは高く、試行錯誤が続いたといいます。ショートステイには「福祉型」か「医療型」という選択肢がありますが、医療型の場合は重症児者およびご家族のことを理解している医師の確保と都道府県ごとの医療審議会において審議される病床の確保が必要となります。福祉から始めたソルウェイズにとってはとても高いハードルで、当初は福祉型で計画を進めるしかありませんでした。一方で、利用者が高度な医療的ケアを必要とするため、福祉型では人材確保や採算面で難しさがありました。土地や資金、人材の課題に直面しながらも、運上夫妻は「子どもたちが楽しくお泊りできる場を作りたい」という揺るぎない思いで、全国の優良施設を見学し、当事者家族の意見を聞きながら試行錯誤の日々を送りました。
転機となったのが、運上夫妻の娘の主治医である田村卓也医師への声がけでした。田村医師に計画への協力を仰ぎ、承諾を得られたのです。田村医師は重症児のケアと同時に地域の小児科としての役割を果たすことを希望。運上夫妻は、「医療型ショートステイに地域の小児科クリニックや病児保育を併設することにより、重い障害のある子どもたちだけでなく、すべての子どもたちに対して、より大きな役割を果たせるのではないか」と、新たなプランニングを進めることができ、約1年の建設期間を経て、2025年5月に『こども未来支援拠点“あいのカタチ”』がオープンしました。

あいのカタチは、医療的ケア児に対応した「医療型ショートステイ」、小児科クリニック、病児保育、児童発達支援、放課後等デイサービス、生活介護、カフェスペースを含む複合型の福祉施設です。
中心となる医療型ショートステイ『レスパイトハウス コタン』は、医療的ケアに対応した「地域こどもホスピス」の機能を持ち、希望する家族にはファミリー利用として一緒に泊まることも可能です。人工呼吸器の管理や頻回な痰の吸引も夜間を通して対応することで、当事者家族の充分なレスパイトを可能にします。また、泊まることができるだけでなく、交流や療育、レクリエーションも取り入れ「おばあちゃんの家に泊まりにいく」「友達とお泊り会をする」という感覚で訪れることができる場にしています。

「泊まる機能があるだけではだめなのです。例えばショートステイを嫌がって食事をとらないというケースもあります。いつもの環境、家族と離れて泊まる子どもたちが、不安になったり嫌がったりせず、楽しみにしてくれることが何より大事です」と昌洋さん。念願の施設が完成し、2025年5月5日に開所式が行われました。
開所式は支援者主体ではなく、あくまで「子どもを真ん中にした式典」となりました。佳江さんは「ここを利用してくれる子どもたちが、この地域で一緒に育っていく姿をみんなに知ってもらいたい」と語り、開所式の意味を子どもたちに特別に感じてもらうことを最優先に考えました。
テープカットの主役として、運上さん自身の娘をはじめとした医療的ケアが必要な子どもたち、そしてスタッフの子どもたちも参加しました。このテープカットは、この施設が子どもたちのためにあることを示す大切な瞬間でした。
また、開所式のプログラムの一環として、子どもたちが選んだ曲『世界中のこどもたちが』を歌い、演奏する場面も設けられました。
「子どもたちが前に出てその場を作り上げることで、どんな場所なのか自然と理解してもらえると思っています」と佳江さん。開所式は、子どもたちが中心となる新しい生活がスタートすることを示す重要な瞬間だったのです。運上夫妻は、「これからが新たなスタート」と語り、今後も子どもたちが中心となる施設運営を続けていく意志を新たにしました。

の開所式の様子。
開所してから数か月の間には、当初は想定していなかった問い合わせもあったといいます。「例えば、虐待を受けて大きな病院に入院していた子どもが、その後、地域に戻ってくるときに、『この小児科でフォローしてほしい』といった問い合わせが増えてきています」と佳江さんはいます。実際、開所の前後から月に1〜2件の問い合わせがあり、佳江さん自身もその多さに驚きました。
「医療的ケア児と家族に対する支援を中心に考えていたものの、虐待を受けた子どもたちなど、地域でのケアが必要なさまざまな困難を抱える子どもたちのニーズがあることに気づかされました。実際にクリニックの田村先生が困難を抱えた子どもはもちろん、その保護者とも良い関係性を作りながらフォローにあたっている姿を見て、私たちが目指す方向性を再確認しました」と佳江さんは語ります。

こうした医療的ケアを中心としたサービスを提供するだけではなく、将来的には卒業後の自立支援にも力を入れていく計画です。昌洋さんは、「特に18歳を迎えるとき、現在の制度では十分な支援がない」と、制度が追いついていない現状を懸念しています。
卒業後に社会に旅立つ子どもたちにとって、どのような活動を行いたいのか、どのような居場所で過ごしたいのか、ということを叶えるのは大きな課題です。「1人暮らしをするのか、お家を出るのか、社会活動に取り組むのか」といった選択肢を考えながら、子どもたちの自立を支援していくと共に、それが実現できる社会づくりについても啓発の必要性を感じています。また、看取りの場についても、子どもが家族や友達と共に過ごせて最後まで語り合える場所が必要と考え、今後の計画に組み込んでいます。
さらには、訪問看護や在宅レスパイト事業を通じて支援を拡充するほど、制度に収まりきらない子どもたちの存在も見えてきます。例えば、「難病はあるけれど重度ではない、医療的ケアはないけれど家から出られない」といった制度の狭間にいる子どもたちです。小児科クリニックを通して、そうしたニーズも発見して、自分たちにできることを模索していきたいと語ります。
佳江さんは自身の人生を振り返り、「長女に生まれ親の期待に応えたいという性格で薬剤師としても尽力してきたけれど、医療的ケア児の親となり、ソルウェイズを立ち上げたことは、人生の一大チャレンジになりました」と語ります。
その挑戦を通して「自分の人生を生きている」と感じるようになり、今度は自分の子どもたちにも「チャレンジしてほしい」と強く願っています。実際、医療ケアを受けている長女は「がんばっているお母さんを手伝いたい」と意思表示をしたそうです。この思いを聞いた佳江さんは、長女が自分なりに「やりたいこと」を見つけ、その中で生きる力を育てていることに喜びを感じています。また、昌洋さんは下の二人の子どもたちの様子を通して「きょうだい児問題」にも充分に目を向け、「お互いが、きょうだいがいてよかった」と思えるような支援を目指しています。
地域での生活を実現するためには、当事者や家族、医療・福祉サービスの連携だけでなく、行政、地域社会、家族会との情報共有と交流が不可欠です。ソルウェイズは、このような包括的な支援ネットワークを築き上げることで、地域社会全体が支え合う仕組みを構築し、そのモデルとなることを目指しています。
- NPO法人ソルウェイズ
- ●団体情報はこちら(CANPAN団体DBへ)
- ●2024年度日本財団助成事業
- 医療的ケアに対応した難病の子どもと家族を支える拠点の整備